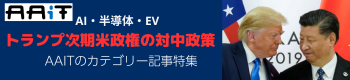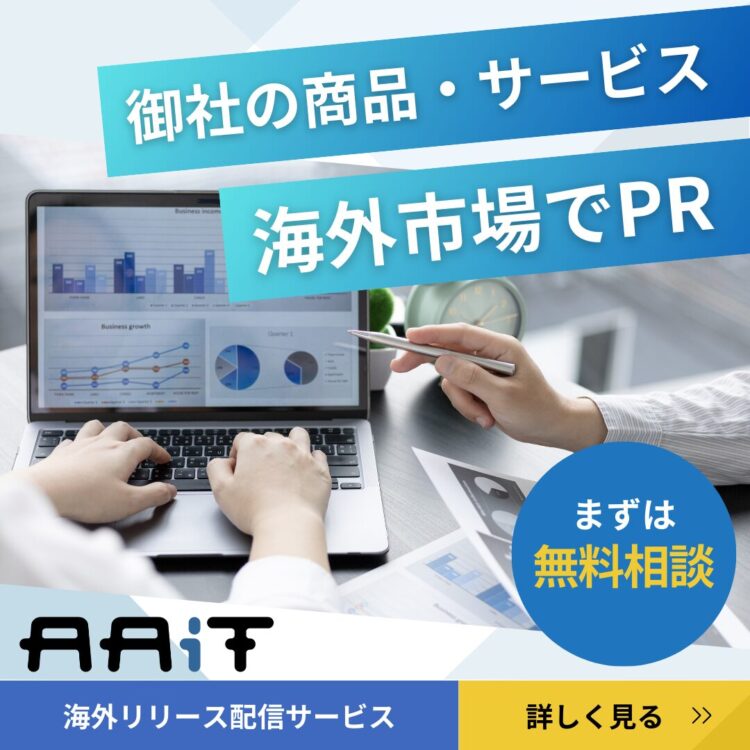HBM5が29年にも商業化へ 性能の鍵は「浸漬式冷却」
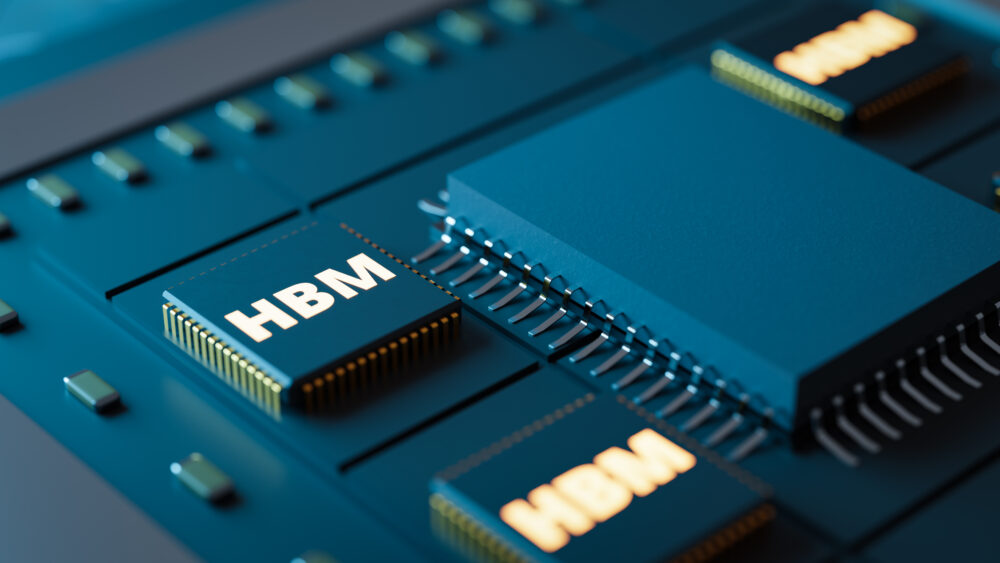
次世代高帯域幅メモリ(HBM5)が2029年にも商業化が見込まれているが、冷却技術が市場競争の主軸になるとみられている。従来、メモリーメーカー各社はパッケージング技術で競ってきたが、今後は冷却能力がその優劣を左右することになりそうだ。
韓国科学技術院(KAIST)電気電子工学部のキム・ジョンホ教授は、自身が率いる学内研究チーム「Teralab」が主催したイベントで、HBM市場の支配力を決める要因がHBM5以降はパッケージから熱処理技術に移行すると指摘した。
同研究室は、2025年から40年に至るHBM4からHBM8までの技術ロードマップも公開。その中では、HBMのアーキテクチャ、冷却方式、シリコン貫通ビア(TSV)の密度、中間層の素材など、複数の技術分野が取り上げられている。
キム教授によれば、異種統合パッケージ技術の発展により、従来は基板下部に配置されていたベースダイ(基本チップ)がHBMの上部に移される可能性があるという。
現在普及が進むHBM4では、GPU(画像処理半導体)の処理負荷の一部をベースダイが担うようになっており、これによりベースダイの発熱量が大幅に上昇。この熱処理が大きな課題となっている。キム教授は、HBM5ではベースダイとパッケージ全体を冷却液に浸す「浸漬式冷却」構造が採用されるとし、HBM4で採用されている上部ヒートシンクへの液冷注入方式には限界があると述べた。
さらに同教授は、現在のTSVに加えて、今後のHBMでは熱伝導ビア(TTV)、ゲートTSV、電源TSV(TPV)といった複数の新たな貫通構造が導入されると説明。HBM7では、DRAMチップ間に冷却液を流し込む「埋込型冷却技術」が必要となり、そのために液体用TSV(流体TSV)が新たに設計される見込みだ。
また、HBM7では高帯域フラッシュ(HBF)などのアーキテクチャとの統合も予定されており、NANDフラッシュがDRAM同様に3D積層される。さらにHBM8では、HBMを直接GPUチップ上に積層する構造が登場する可能性があるという。
キム教授は、冷却技術に加えて接合プロセス(ボンディング技術)もHBM競争における鍵になると述べた。特にHBM6以降はガラスとシリコンのハイブリッド中間層が導入される予定で、これが冷却効率や構造の安定性向上に寄与するとみられている。
今後のHBMの進化は、単なる容量や帯域幅の拡張だけでなく、熱制御技術や接合技術といったパッケージング以外の周辺技術の革新が大きな差別化要因となることが示唆された。
(500×80px)(450×80px)(460×80px)(470×80px)(2).png)