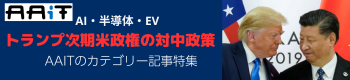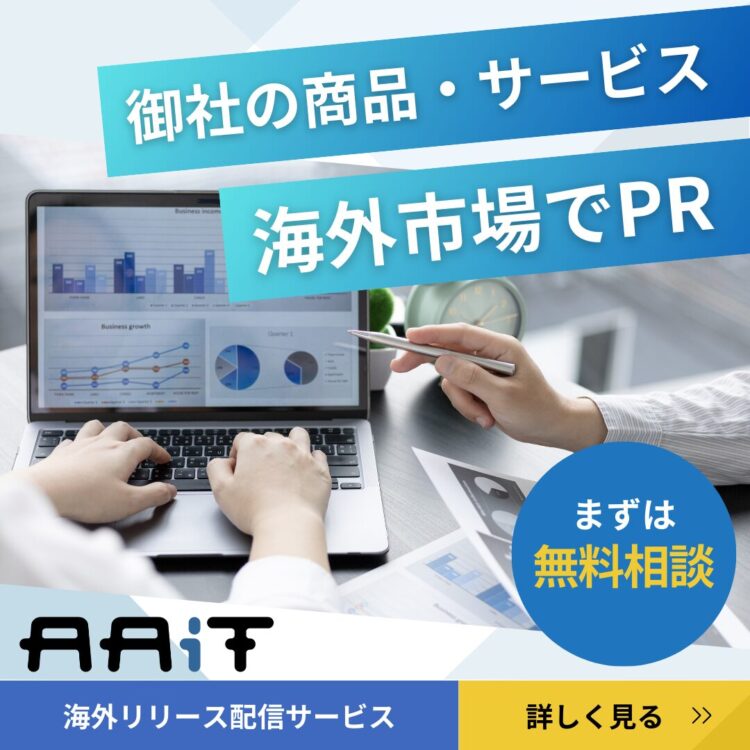DDR4の終焉、中国国産CPUに訪れる試練

サムスン電子、SKハイニックス、Micron Technology(マイクロン・テクノロジー)によるメモリ「DDR4」の生産停止が、中国国産CPU(中央演算処理装置)に試練となりそうだ。DDR5に対応したCPUが少ないためで、華為技術(ファーウェイ)の「鯤鵬920」、海光の「3号73XX」、兆芯の「KH-4000」、龍芯の「3C6000」など、いずれもDDR4までしか対応していないのが現状だ。
今年5月初旬から、DDR4の価格が継続的に上昇。中でも人気のある型番「DDR4 16Gb 3200MHz」は、5月6日時点で2.4ドル(約352円)だったものが、わずか数週間で6.4米ドルへと跳ね上がり、160%を超える高騰を記録した。
しかも今や、同条件のDDR5よりもDDR4の方が高値で取引されており、「価格逆転」という異例の事態も起きている。業界関係者も「生産終了間近のDDRがここまで値を上げたのは前代未聞」と驚きを隠さない。
DDRメモリは、CPUの演算能力を引き出すための重要な記憶装置で、その技術仕様はCPUの性能限界を直接左右する。しかし、現在の国産CPUの多くはDDR5に対応しておらず、DDR4の終息とともにその影響を受けることになる。
市場に走る動揺
DDR4の価格高騰の背景には、3大メモリメーカーによる相次ぐ生産終了の動きがある。
Micron Technology(マイクロン・テクノロジー)の幹部はDDR4およびLPDDR4Xの生産終了を正式に発表。すでに顧客に通知済みで、PCやデータセンター向けの製品供給も停止に向かうという。サムスン電子、SKハイニックスもまた、DDR4の生産終了を通知しており、最終受注期限を6月初旬に設定している。
製造元から見れば、DDR4の役目は終わり、より高度なプロセスへの転換が求められている。これまでもDDR2やDDR3が同様にフェードアウトしてきたように、DDR4も時代の流れとして自然な引退である。
例えば、DDR2は2003年に登場し、サムスンが正式に製造終了したのは21年。約18年間市場に存在した。DDR3は08年から量産され、23年にSKハイニックスが出荷停止、約15〜16年のライフサイクルだ。
DDR4は14年に登場し、25年でその幕を閉じる。ライフサイクルはわずか11年と短縮傾向にある。これは単なる技術進化だけではなく、「儲けが少ない製品は早く切り上げる」というビジネス判断も背景にある。
事実、DDR5は周波数・帯域・容量のすべてにおいてDDR4を上回り、AI(人工知能)処理や4K編集といった負荷の高い用途にも対応可能だ。さらに、HBM(高帯域メモリー)の市場拡大により、各社はより高付加価値の製品にリソースを集中している。SKハイニックスでは、HBMがDRAM出荷量の14%に過ぎないにもかかわらず、売上の44%、利益の54%を生み出しているという。
こうした流れにより、DDR4は他の世代に比べ、より劇的に退場していく運命にある。
一方、ユーザー側では事情が異なる。価格の安さからDDR4を支持するサーバーや企業はまだ多く、コスト面での「使い得感」が根強い。また、IntelのRaptor LakeやIce LakeなどもDDR4専用であるうえ、中国国内でも多くのCPUがDDR4にしか対応していない。
その結果、供給と需要の不均衡が生じ、DDR4価格の「異常な高騰」が続いている。
海外メーカーと「世代差」
DDR5の普及という点で、海外大手と中国国内メーカーの間には依然として「世代差」がある。
Intel(インテル)は21年に登場した第12世代プロセッサ「Core」からDDR5を正式サポート。すでに「Core Ultra 200」シリーズなど、最新のプロセッサはDDR5が標準で、「H610」などのローエンドマザーボードにもDDR5対応モデルがある。
米半導体大手、Advanced Micro Devices(AMD、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)も同年にZen4アーキテクチャの「Ryzen 7000」シリーズでDDR4を完全に切り捨て、DDR5への移行を完了。サーバー向けの第4世代EPYCやEPYC 4005もすべてDDR5をサポートしている。このように、海外メーカーはCPUの世代交代とメモリ技術の進化をしっかり同期させている。
一方で、中国国内ではDDR5に対応したCPUはまだ少数派だ。たとえば、華為の「鲲鹏920」、海光「3号73XX」、兆芯「KH-4000」、龍芯「3C6000」など、いずれもDDR4までしか対応していない。
短期的にはDDR4がコストパフォーマンスで依然優位だが、DDR5の供給増と価格低下が進めば、その優位性は失われていく。今後、DDR4しか対応しないCPUを採用すると、企業も個人もメモリ価格高騰と適合問題という「二重の負担」を強いられることになる。
また、国内のDRAMメーカーもDDR5の技術を蓄積しているが、CPUとの協調最適化は今後の課題。CPUがDDR4に依存し続ければ、メモリメーカーの技術更新にもブレーキがかかる。PCやサーバーの組み立て企業も、現行ニーズと将来技術のバランスを取りながら、サプライチェーンの高度な管理が求められる。
国産CPUがこの「小さな試練」を乗り越えるためには、DDR5対応製品の研究開発・量産を加速し、内製メモリとの最適な協調エコシステムを築く必要がある。
国産CPU、次なる進化へ
DDR4の終焉は国産CPUにとって「危機」であると同時に、「進化のチャンス」でもある。
まず、DDR4の価格上昇がいつまで続くかが焦点だ。専門家は「上流の価格政策は依然として強気で、特にDDR4は生産終了に伴う先回り需要で第3四半期の価格は30~40%の上昇が予想される」と述べている。受注は殺到しており、工場は5ヶ月連続でフル稼働状態が続いている。「注文は1.5〜2倍に膨れ上がり、供給が追いつかない」と言及。サムスンの在庫は25年末まで、マイクロンは26年第1四半期まで供給可能だと見込んでいる。
一部の小規模企業は、DDR4の「一時的復活」を好機と捉え、生産拡大に動き出している。こうした価格逆転現象はPC・サーバー市場の移行完了まで、3〜5ヶ月は続くと見られている。
一方、海外大手がDDR4を減産することで、中国のDRAMメーカーには市場参入のチャンスが生まれている。最近では、聯想(Lenovo)や浪潮(Inspur)などの大手メーカーも国産CPU+DDR5構成による製品開発に着手。設計段階から新技術を前提に組み込み、生産体制を整えつつある。
そしてDDR5に対応する国産CPUも、いよいよ市場に姿を見せ始めた。
- 華為「鯤鵬920 V200」:最大2.6GHz、メモリー帯域60%向上、IO帯域66%向上、ネットワーク帯域4倍。中国情報安全等級Ⅱ級の認証を取得済み。
- 飛騰「騰雲S5000C」:最大2.3GHz、SPECベンチで整数1300点/浮動小数1170点を記録し、DDR5を完全サポート。
- 兆芯「KX-7000」:最大3.5GHzのx86互換CPU。DDR5対応に加え、PCIe 4.0、SATA、USB、HDMI、DPなどもワンチップで対応可能な完全統合型設計。
こうした進展は、国産CPUが次の時代に向けて確実に歩を進めていることを示している。
(500×80px)(450×80px)(460×80px)(470×80px)(2).png)