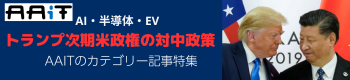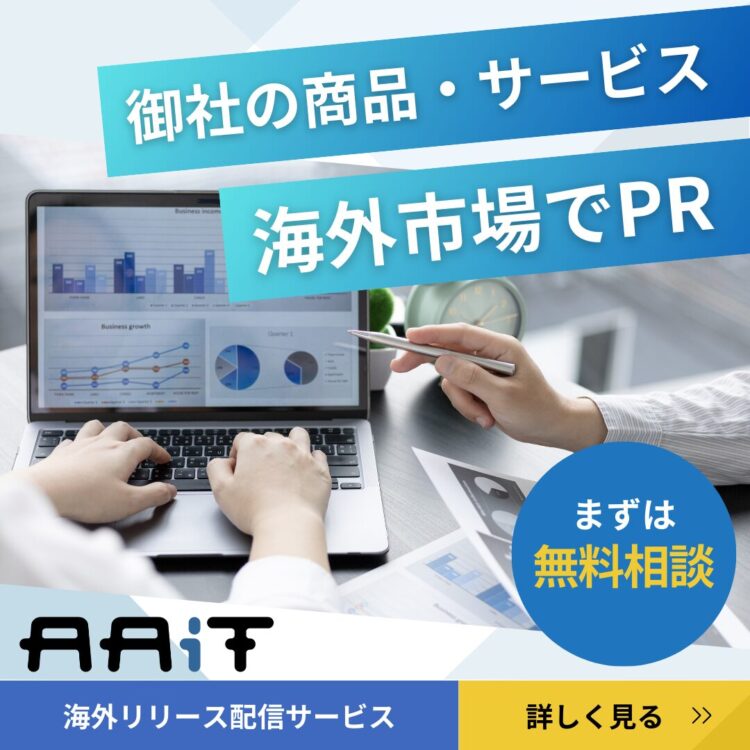長シン存儲技術が上場へ、内製メモリーの採用比率も着実に拡大

中国証券監督管理委員会(CSRC)の公式ウェブサイトによると、中国の国産DRAMメーカー、長シン存儲技術(シンは金が3つ、CXMT、安徽省合肥市)が上場(IPO)に向けた企業指導を開始した。中国で内製された国産メモリーの採用比率も高まる中、資金調達で開発力を高めていく計画だ。
長シン存儲技術は中国国内における主要なDRAMチップメーカーの一つで、2016年に設立。会社に支配株主はおらず、筆頭株主は合肥清輝集電企業管理合夥企業(有限合夥)で、同社株式の21.67%を保有している。
DRAM(動的ランダムアクセスメモリ)は、NAND型フラッシュメモリとともに世界のメモリチップ市場の大部分を占めている。現在、DRAMとNAND Flash市場の大半は海外企業が支配しており、台湾のTrendForceのデータによると、2025年第1四半期(1〜3月)時点でSKハイニックス(36%)、サムスン(33.7%)、マイクロン(24.3%)の3社で市場の94%を占めている。
国内メーカーの巻き返しも進んでいる。TrendForceの調査では、ウエハー生産能力ベースでみると、24年の長シン存儲技術のDRAM生産量は世界全体の10%未満とされる。今年は総合的な生産能力や品質の向上により、国内メモリメーカー全体で10%程度のシェアに達すると予測されており、前年比で倍増となる見通しだ。
別の調査会社Counterpointの5月の報告によると、今年第1四半期の長シン存儲技術のビット(bit)ベースでの市場シェアは6%で、前年同期と同水準だったが、第4四半期には7.5%まで拡大するとみられている。6月更新の別の報告では、DDR4およびLPDDR4分野でのシェアはそれぞれ10%、20%に達している一方、DDR5およびLPDDR5市場でのシェアは現時点で1%未満にとどまり、年末にはそれぞれ7%、9%に成長する見通しが示されている。
DDR4とDDR5は、それぞれ第4世代および第5世代の同期型DRAMであり、主にパソコンやサーバーのメモリとして使用される。DRAMのDDR4チップが依然として海外メーカー由来であるとする一方で、一部の国内ブランドではすでに国産チップが使われているもようだ。近年、海外メーカーがDDR4の生産を減らし、DDR5やHBM(高帯域メモリ)へとシフトしていることから、国内メーカーにとって市場シェアを拡大する好機となっているとの業界関係者の見方もある。
第一財経によると、国内モジュールメーカーの担当者は「これまでのところ輸入チップの使用比率は80~90%に上っていたが、各社とも国産チップの採用割合を徐々に増やしており、品質向上に伴ってコスト面での競争力も高まりつつある」と指摘。以前は主にサムスン電子製を使用していたが、現在では新たなプロジェクトでは国産チップが優先的に検討されているという。
とはいえ、長鑫科技を含むDRAMメーカーがより先進的な製品を開発するには、高誘電率金属ゲート(HKMG)技術といった技術的課題の克服が不可欠だ。Counterpointはこの技術的障壁を理由に、5月に長シン存儲技術の生産予測を下方修正している。
メモリチップは現在、3Dスタック技術によって性能を高めており、AI(人工知能)チップとの統合が進むHBM(広帯域幅メモリー)も複数のDRAMチップを垂直に積層して構成されている。HBM3eやHBM4の量産・開発を進める海外大手であっても、技術的なハードルは依然として高く、中国メーカーもこれを乗り越えることが課題となっている。
25年版の胡潤世界ユニコーン企業ランキングによると、同社の評価額は1600億元で、世界21位にランクインしている。一方、兆易創新が3月に開示した資料によれば、長シン存儲技術はIPO前に108億元を調達予定で、評価額は1400億元(約3兆2000億円)とされている。
(500×80px)(450×80px)(460×80px)(470×80px)(2).png)