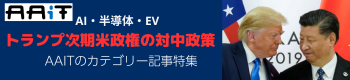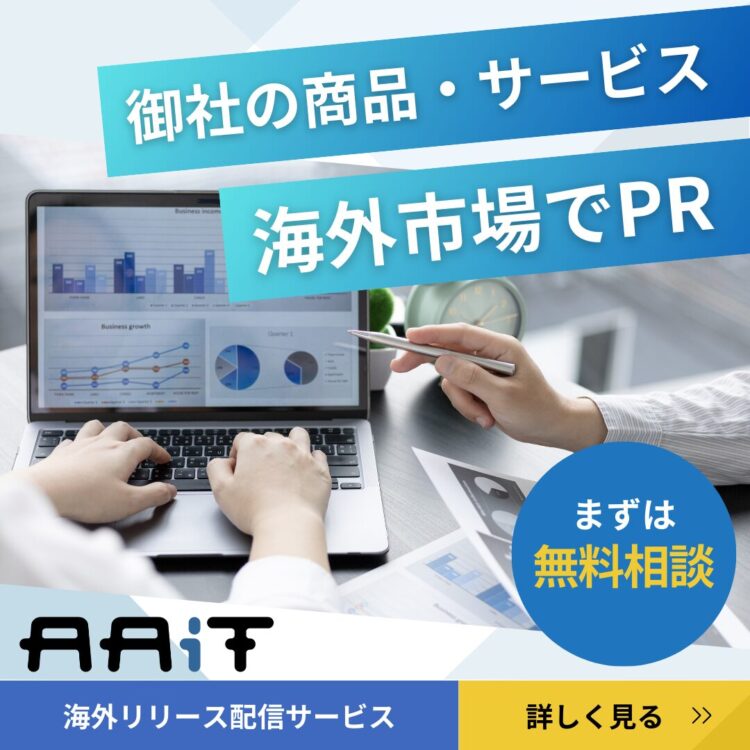中国の産業用ロボット、25年上期の輸出額が6割増
ベトナム・メキシコ・タイが主要成長市場に

中国の産業用ロボットの海外輸出が勢いを保っている。中国海関(税関)総署がこのほど発表したデータによると、2025年上半期(1〜6月)における中国の産業用ロボット輸出台数は9万4200台で、輸出額は前年同期比で59.74%増加の7億4600万米ドル(約1092億8900万円)に達した。
同統計の産業用ロボットには、塗装ロボット、汎用工業ロボット、協働ロボット、IC(集積回路)工場向け自動搬送ロボット、抵抗溶接ロボット、金属加工用アーク・プラズマ・レーザー溶接ロボットなどが含まれる。
24年通年の産業用ロボット輸出額は、前年比43.22%増の11億3000万米ドルだった。税関総署によると、昨年の中国の産業用ロボット輸出は世界シェアで第2位に躍進しており、25年もその成長傾向は継続している。
界面新聞によると、高工機械人産業研究所は、急成長の背景に2つの要因があると指摘する。ひとつは、世界の製造業がスマート化・自動化へと急速に移行していること。特に新エネルギー車(NEV)や太陽光発電といった産業でロボット需要が急増しており、ベトナム、インド、アメリカなどが中国ロボットの主要輸出先となっている。
もうひとつは、産業チェーンの東南アジアや欧州への移転に伴う新興市場の拡大である。ベトナムやタイなどは中国の産業チェーンを受け入れる形で、産業用ロボットの新たな輸出先として急成長している。
税関データに基づく界面新聞の集計によると、25年上半期における中国の産業用ロボット最大の輸出先はベトナムで、輸出額は8635万米ドルに達し、前年同期比で倍増以上の伸びを見せた。
続いてメキシコとタイが2位・3位となり、いずれも輸出額が大幅に増加した。メキシコ向け輸出額は前年同期比274.78%増の5922万米ドルという驚異的な伸びを記録している。
トップ10の輸出先のうち、韓国とドイツへの輸出額のみが前年同期比で減少したが、他の国々は軒並み増加。特にロシアやポーランドなどへの輸出額は前年比で3桁増となった。
国産メーカーが台頭
近年、国産ロボットの台頭により、従来外資に支配されていた中国の産業用ロボット市場は構造的な転換期を迎えている。調査会社MIR DATABANKによると、24年には中国国内における国産ロボットメーカーの市場シェアが52.3%に達した。
さらに同社の24年世界産業用ロボット出荷ランキングによると、上位10社のうち4社を中国企業が占めており、南京埃斯頓自動化(ESTUN)、深セン市匯川技術(Inovance Technology)、埃夫特智能装備(EFORT)、珞石北京科技(ROKAE)が名を連ねている。なお、17年にはランクインした中国企業は1社のみだった。
高工機械人産業研究所は、海外の大手メーカーと比較して、中国製ロボットは搬送やパレタイジングといった用途でコストが低く、納期も約30%短縮できることから、中小企業の需要に適していると指摘する。また、中国国内ではサプライチェーンの反応速度がより重視されており、地場企業は迅速なアフターサービスを提供できる一方で、外資系は部品調達に時間がかかりコストも高いという。
現在、国内市場では需要が減速し競争が激化しているため、価格と利益が圧迫される中で、海外市場への進出を図る中国企業が増加している。
「中国区域経済50人フォーラム」の公式アカウントによれば、河南省社会科学院の元院長である張占倉氏は、「完備された産業基盤と低コストが、中国製ロボットに国際市場での強力な競争力を与えている」と述べている。
また、スイスのABBやデンマークのユニバーサルロボットなどの海外大手企業も中国市場への投資を強化しており、中国からの輸出をさらに後押ししている。
高工機械人産業研究所は、今後3〜5年は輸出拡大が続くとしつつも、長期的には高付加価値技術の開発や貿易障壁への対応が不可欠だと警鐘を鳴らす。また、「安さ勝負」の戦略から脱却し、海外市場での長期的なブランド構築が必要だと指摘する。「今後は、コア部品の開発や国際基準への適応、ブランド価値の向上がカギとなります。コストパフォーマンスに優れる代替製品から、技術をリードする存在への転換を図り、ヒューマノイドやAI(人工知能)協働ロボットといった高付加価値製品によって、中国製ロボットのブランドを再定義していく必要がある」としている。
(500×80px)(450×80px)(460×80px)(470×80px)(2).png)