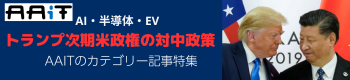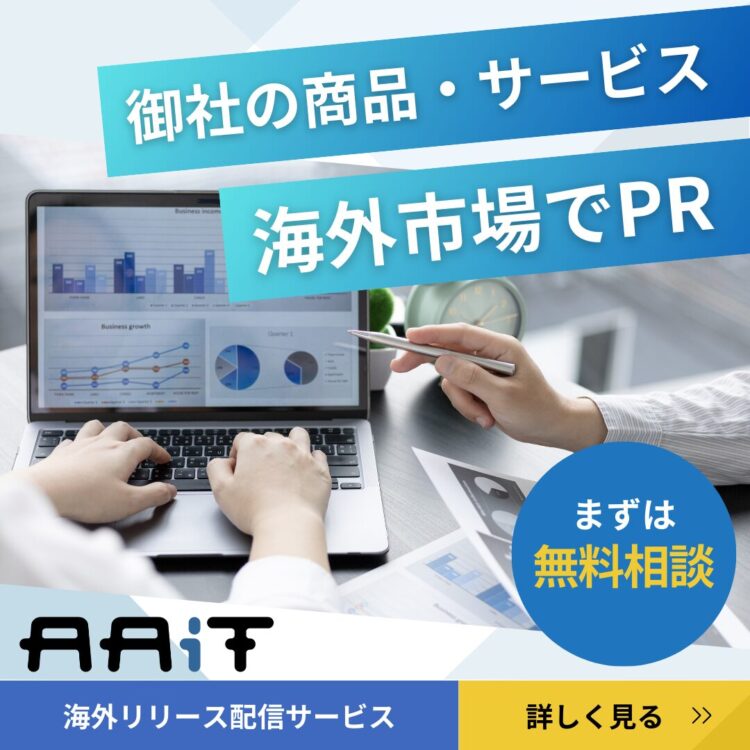中国の「衛星コンステレーション」計画、2事業が打ち上げ常態化

宇宙ビジネスの分野で、中国が米国を猛追している。一定の軌道上に多数の人工衛星を打ち上げて、一体的に機能させる「衛星コンステレーション」の構築においては、イーロン・マスク氏率いる米SpaceXが世界を大きくリードしているが、中国でも3つの巨大衛星コンステレーション計画が進行中。うち2プロジェクトは常態的に衛星を打ち上げる段階に入った。
中国で進められている3プロジェクトは、中央企業、星網集団の「国網星座」、上海市の国有企業、上海垣信衛星科技の「千帆星座」、藍箭科技傘下の鴻擎科技の「鴻鵠星座」。いずれも最終的に1万基を超える規模の衛星コンステレーションを構成する計画で、そのうち、星網集団と千帆星座は定期的な衛星の打ち上げが可能になった。
国網星座は、通信・インターネットインフラを構築するための“国家隊”として、昨年末に衛星10基を搭載したロケットを初めて打ち上げ、今年2月に第2陣の打ち上げを行った。
千帆星座は「地方隊」の代表格で、運営主体の上海垣信衛星科技には、上海市政府系の組織や現地企業が出資している。これまでに5回の打ち上げで合計90基の衛星を配置。直近では、3月12日未明に海南省文昌市に整備された中国初の商業宇宙発射場から運搬ロケット「長征8号遥6」の打ち上げに成功した。
しかし、中国の衛星コンステレーション計画は足元で、衛星の生産能力にロケット発射能力が追い付かないというジレンマがある。
例えば、千帆星座で用いる衛星は、中国科学院微小衛星創新研究院と上海格思信息技術の2社が製造を進めており、海格思信息技術だけでも23年の工場稼働時の年間生産能力は300基に達した。一方で、千帆星座は24年8月6日から現在までの期間に5回の打ち上げが行われ、45日ごとに平均18基の衛星が発射された計算だ。このペースのままでは、2025年に648基の衛星打ち上げを完了とする当初の計画の達成が難しい。
国網星座も、向こう5年で計画総数の約10%に当たる1000基超の衛星の打ち上げを予定しており、同じく打ち上げ能力が課題となっている。
中国の各地方政府は足元で、商用宇宙ビジネスの育成に力を入れている。商業宇宙ビジネスは、23年の中央経済工作会議で戦略性新興産業として取り上げられて以降、24年と25年の2年連続で、政府活動報告に組み入られた。こうした流れの下で、これまでに17の省・直轄市が商用宇宙ビジネスに関連した産業政策を多数打ち出した。
うち、上海市は、2025年末に年間50基の商用ロケットと600基の商用衛星を製造する能力を構築する目標を提示した。北京市では、北京経済技術開発区が位置する亦庄地区が、今年は昨年の3倍となる延べ40回のロケット打ち上げを行い、130基の衛星を軌道投入し、さらに28年には100回に迫るロケット打ち上げで、2000基の衛星を配備するとの計画を定めた。
(500×80px)(450×80px)(460×80px)(470×80px)(2).png)